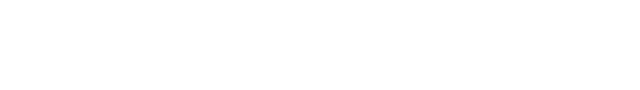緑内障
①よく見られるタイプの緑内障/正常眼圧緑内障、開放隅角緑内障
エビデンス(証拠)のある治療は眼圧を下げることです。多くは点眼薬で経過を見ますが、状態によっては選択的レーザー線維柱帯形成術SLT(当院に設置)や、入院による緑内障手術が必要になることがあります。選択的レーザー線維柱帯形成術は過去に行われていたアルゴンレーザーによるものと眼圧下降効果は同等とされていますが、合併症が少なく、高い効果が示されることもあります。
目標眼圧は状況によってゴールが動きます。一般には、もとの眼圧より20%減が目標となります。多数の人と同じ眼圧15〜16mmHg、より低い12mmHgを目標とすることもあります。主に視野欠損の状態やその進行スピードを考慮して判断しますが、年齢、角膜厚、家族歴など他の要因も考える必要があります。
眼圧が低値でも視野の進行が著しい時は入院検査をして頂くことがあります。
②発作タイプの緑内障/原発閉塞隅角緑内障
瞳の付け根(隅角)が狭くなって塞がり、急に眼圧が上昇します。頭痛、眼痛、霧視を自覚し、治療は急を要します。急性期は、点滴、内服、点眼で眼圧を下げます。落ち着いてから水晶体を除去し眼内レンズを挿入します。YAGレーザーを用いることもあります。
③他に特殊な病型として、落屑緑内障 、ポスナー・シュロスマン症候群、続発性緑内障があります。